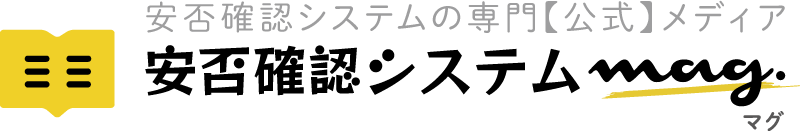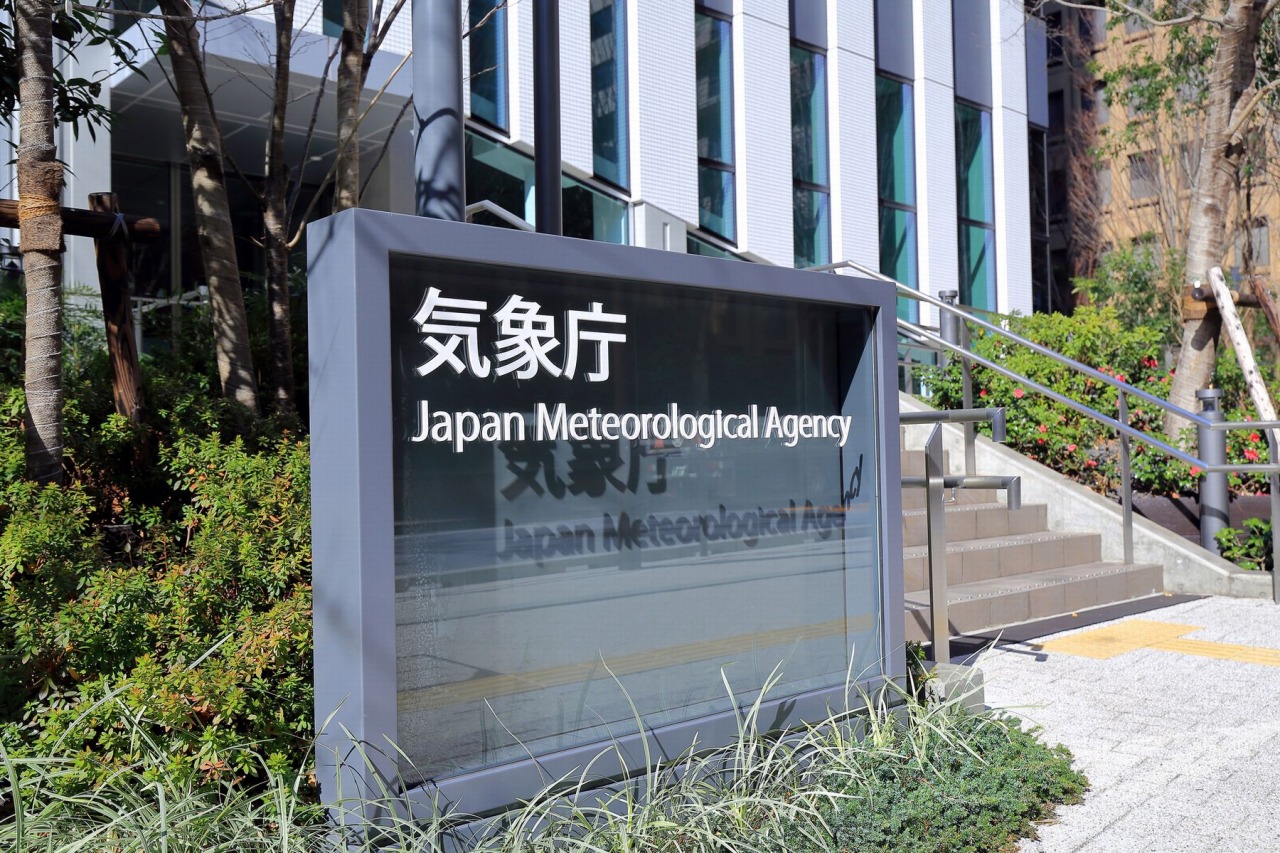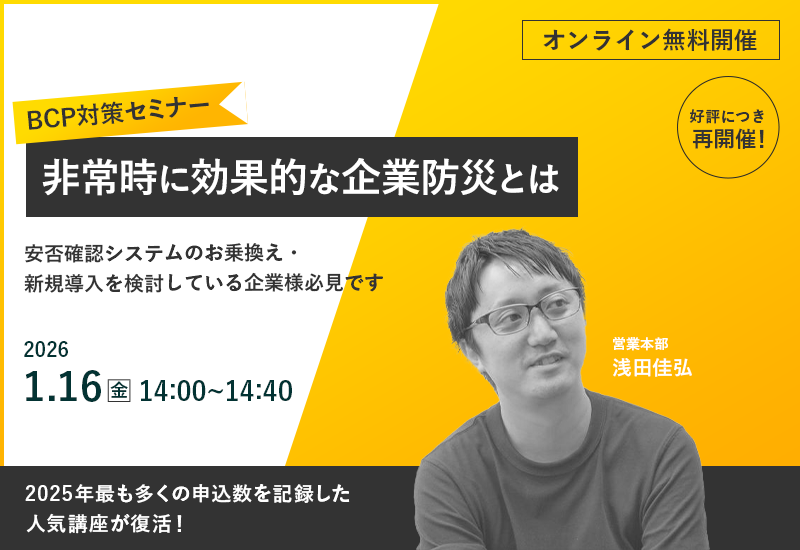安否確認で社員を守る!今こそ始める災害対策
2025/11/27.

災害や緊急事態がいつ起こるか、私たちには予測できません。そんな「もしも」に備えるために、企業が取り組むべき最優先事項のひとつが「人を守ること」、つまり従業員の「安否確認」です。
このコラムでは、「人的資源の保護」に焦点を当て、「安否確認」の重要性や「安否確認システム」導入のメリット、実際の成功事例、選定のポイント、そして今すぐ始められる具体的な対策まで、わかりやすく解説していきます。
BCPをこれから考える方も、見直したい方も、「人」を守る視点から、一緒に見直してみませんか?
index
事業継続計画における「安否確認」の重要性とは

企業が自然災害や大規模トラブルといった「もしも」に備える上で、まず最優先すべきは「人」の安全です。どれほど緻密な事業継続計画(BCP:BusinessContinuityPlan)を立てていても、社員の無事が確認できなければ計画は絵に描いた餅になってしまいます。それほどまでに「BCPにおける安否確認」は要の要ともいえる存在です。
災害発生時、真っ先に求められるのは「誰がどこで、どうしているのか」という情報です。なぜなら社員が無事でいるかどうかがわからないまま、業務の再開を判断するのは非常に難しいものだからです。こうした状況下では、「迅速な安否確認」こそがBCP発動の第一歩なのです。
例えば、東日本大震災の際、多くの企業が社員の安否を把握するのに数日を要したという事例があります。当時、まだ「安否確認システム」を導入している企業は少なく、多くの企業は電話やメール、社内連絡網を使い安否確認を行いましたが、この遅れが結果として業務再開や取引先との連携に悪影響を与えました。一方で、あらかじめ「安否確認システム」を導入していた企業では、発災後数時間以内に社員の約9割の安否を確認できたという報告もあります。これは、被災後の混乱を最小限にとどめるうえで非常に大きな差となりました。
また、「安否確認」は社員自身の安心にもつながります。自分の居場所や無事を会社に伝えられる手段があること、同僚の無事を把握できることは、大きな精神的支えになります。つまり、「安否確認」は単なる情報収集ではなく、企業と社員の「信頼」をつなぐ架け橋でもあるのです。
さらに最近では、感染症やテロ、サイバー攻撃など多様なリスクが複雑化しています。こうした新たな脅威に対しても、従業員の安否や健康状態を把握する機能は、BCPの中核として求められています。特にリモートワークが普及する中で、「誰が・どこで・どのような状況にあるのか」を見える化することは、組織の柔軟な対応力を支える重要なポイントです。
「安否確認」を人海戦術で行うのは現実的ではありません。だからこそ、「安否確認システム」のように、安否確認を効率的かつ確実に行える仕組みが不可欠です。
BCPにおける「安否確認」は、単に形式的な作業ではなく、「人命を守り、組織を動かす最初の一手」だといえるでしょう。そしてその実効性を高めるためには、適切な「安否確認システム」の導入と定期的な訓練が欠かせません。
次章では、その「安否確認システム」が具体的にどのような役割を果たし、導入によってどんなメリットが得られるのかを掘り下げていきます。BCPを机上の空論に終わらせないためにも、まずは「安否確認」のあり方を見直すことから始めてみましょう。
「安否確認システム」の導入メリット

災害や突発的なトラブルが起きたとき、企業が最初に直面する課題は「社員の無事がすぐにわかるかどうか」です。前章でお伝えしたように、BCPにおいて「安否確認」は「最初の一歩」。その一歩をスムーズに、そして確実に踏み出すために、今や多くの企業が「安否確認システム」を導入しています。今回はその導入によって得られるメリットについて、具体的にご紹介していきます。
1.迅速で確実な安否把握ができる
災害直後は通信回線の混雑やインフラ障害で、電話やメールがつながりにくくなることがあります。そうしたときでも、「安否確認システム」は専用のサーバやクラウドを経由して、複数の通信手段(メール、SMS、アプリ通知など)を同時に使えるのが特長です。そのため、より多くの社員とスピーディに連絡を取ることができます。
また、回答状況がリアルタイムで一覧表示されるため、「誰が未回答か」も一目でわかります。手作業では把握が難しい情報も、システムなら数分で集約・可視化できるのは大きな強みです。
2.業務再開の判断を早められる
社員の安否がすぐに確認できれば、その時点で「業務を再開できるか」「誰が対応可能か」の判断が下せます。例えば、物流部門の社員が無事かどうかがわかれば、出荷の再開可否を決めやすくなりますし、リモートで対応可能なスタッフを把握できれば、災害当日からの最低限の業務維持も可能になります。
つまり、「安否確認システム」の導入は、事業復旧のスピードアップにもつながるということなのです。
3.社員への安心感と信頼構築にも寄与
「何かあったとき、会社はちゃんと自分の安否を気にしてくれる」。この安心感は、社員にとってとても大切なものです。「安否確認システム」は、双方向のコミュニケーションが取れる設計になっているものも多く、社員が自分の状況を簡単に報告できる環境があるだけで、心理的安全性が高まります。
また、同僚や上司の無事がわかることも大きな安心材料となり、チームの一体感を保つことにもつながります。企業として「人を大切にしている姿勢」が表れる場面でもあります。
4.災害以外の非常時にも応用可能
「安否確認」と聞くと、大規模災害だけを想像しがちですが、実は感染症の流行や停電、通信障害、テロ、サイバー攻撃といった非常時にもこのシステムは有効です。コロナ禍では、体調報告や在宅勤務状況の確認にも活用されました。
「安否確認システム」は「緊急時の連絡インフラ」として企業活動のあらゆる局面で活躍できるのです。
5.業務負荷の軽減と属人化の回避
これまで「安否確認」を人力で行っていた企業では、担当者にかかる負担が非常に大きかったはずです。「連絡漏れがないか」「全員に連絡が届いたか」と神経をすり減らす作業は、ストレスも時間もかかります。
しかしシステムを導入すれば、一斉通知や自動集計、未回答者へのリマインド送信などを自動化できます。属人化も避けられ、誰が対応しても同じレベルの確認が行える体制を作れるのは大きなメリットです。
まとめ:導入は「備え」の第一歩
このように、「安否確認システム」は、単に安否を尋ねるだけのツールではありません。「社員の安全・事業の継続・会社の信頼」を守る、非常時のライフラインともいえる存在なのです。
もちろん、導入するだけで安心というわけではなく、使い方を定着させるための訓練や運用体制の整備も必要になります。その点については、次章で実際の導入事例を交えながら、よりリアルな視点で解説していきます。
企業として、最悪の事態にどう備えるのか――その答えの一つが、「安否確認」の仕組みを整えることなのです。
災害時における人的資源保護の実践例

企業にとって、災害時に最も優先されるべきは「人を守る」こと。どんなに立派なBCPを策定していても、従業員の安否が把握できなければ機能しません。ここでは、当社の安否確認システム「安否コール」を導入して、人的資源の保護に成功している3社の具体的な事例をご紹介します。
事例1:静岡済生会総合病院様
10代から80代まで幅広い職員が在籍する静岡済生会総合病院様では、誰でも簡単に使える安否確認手段が求められていました。そこで導入されたのが「安否コール」。スマートフォン・PC・ガラケーにも対応しており、災害時の安否確認はもちろん、新型コロナウイルス流行時の出勤確認など日常の業務でも活用されています。職員の不安を和らげると同時に、管理者の業務負担も軽減し、人的資源管理の信頼性向上に寄与しています。
https://www.anpi-system.net/blog/detail.php?c=30
https://www.anpi-system.net/result/detail.php?w=29
事例2:東亜電機工業株式会社様
東亜電機工業株式会社様は、地震や集中豪雨などの自然災害に直面し、従来の手動による安否確認方法では対応が困難であることを痛感して「安否コール」を導入しました。システムの導入により、災害発生時には自動で安否確認の通知が送信され、従業員からの回答も迅速に集計されるようになっています。例えば2024年の能登半島地震では、発生から30分以内に従業員の約25%から回答が得られ、翌日には社長への報告が可能となりました。システム導入による「安否確認のDX化」は、従業員の安全確保と事業継続に大きく寄与しています。
https://www.anpi-system.net/blog/detail.php?c=405
https://www.anpi-system.net/result/detail.php?w=44
事例3:株式会社東洋内燃機工業社様
株式会社東洋内燃機工業社様は、遠隔地で作業中の従業員や夜間や休日における安否確認の連絡手段の確保が課題となっていました。2023年の北陸地震を契機に、同社は「安否コール」を導入しました。このシステムにより、従業員の安否情報を迅速に収集・集計できるようになり、特に2024年の能登半島地震の際には、手動配信を通じて全従業員の無事を短時間で確認することができました。「会社は従業員を見守っている」というメッセージを伝えることで、従業員の安心感と信頼感が向上しました。
https://www.anpi-system.net/blog/detail.php?c=441
https://www.anpi-system.net/result/detail.php?w=48
まとめ:共通する成功のポイント
これらの3社に共通するのは、「誰でも・すぐに・確実に使える」ことを前提にした安否確認システムの活用です。加えて、日常的な活用・継続的な訓練・通信手段の多様化が、人的資源を守る強固な体制を築いています。
BCP対策の中で、安否確認体制の整備は「最初にして最も重要な一歩」。次章では、そのシステムを選ぶ際に確認すべきチェックポイントをご紹介します。
「安否確認システム」選定のチェックポイント

「安否確認」の体制づくりにおいて、どのような「安否確認システム」を導入するかは非常に重要な課題です。適切なシステムを選ばなければ、せっかくのBCPも機能不全に陥ってしまう可能性があります。
これまでの章でお伝えしてきたように、「安否確認システム」は、災害時における初動対応の柱であり、人的資源を守るための要です。本章では、数多くあるシステムの中から「自社にとって最適な一つ」を見つけるために、どんな点に注意すべきかをわかりやすく整理してご紹介します。
1.操作性のわかりやすさは最優先ポイント
いくら高機能なシステムでも、使う側が戸惑ってしまっては意味がありません。特に災害時は混乱が生じやすく、誰でもすぐに操作できることが求められます。
- パスワード不要でログインできる仕組み
- ワンタップで回答できるUI(ユーザインターフェース)
- スマートフォン・ガラケー・PCに対応しているか
など、「ITに不慣れな人でもすぐ使える設計かどうか」は必ずチェックしましょう。現場や高齢の従業員が多い企業では、シンプルさが命綱になります。
2.多様な通信手段に対応しているか
災害時はインフラが不安定になるため、複数の連絡経路を持つことが大切です。メールだけでなく、SMS、アプリ通知、WEBフォームなど、複数の通信チャネルを使って「安否確認」ができるシステムを選ぶと、リスク分散になります。
また、通信が集中する地震直後でも連絡が届くように、バックアップサーバの整備状況もチェックしておきましょう。
3.回答状況のリアルタイム把握と管理者の使いやすさ
管理者側の機能も非常に重要です。特に以下の点は選定時に注目してください。
- 回答状況が一覧でリアルタイムに確認できる
- 未回答者への自動再通知機能がある
- 組織ごとのグループ管理ができる(部門・地域別など)
- 操作マニュアルやサポート体制が整っている
「安否確認システムを運用できるか」は管理者の負担に直結します。導入後も継続的に扱える仕組みであるか、サポートがどれほど手厚いかも、現場のリアルな視点でチェックしましょう。
4.多言語対応・属性別配信の可否
近年では、多国籍の従業員や外国人技能実習生を雇用している企業も増えています。そのような場合、「安否確認」のメッセージが母語で届くかどうかは重要な要素です。
また、属性別(職種別・勤務地別など)に情報を絞って配信できると、混乱を避け、的確な情報提供につながります。正確な情報を、必要な人に、素早く届ける仕組みがあるかを必ず確認しておきましょう。
5.日常業務にも活用できるか
BCPは「使っていないと忘れてしまう」という側面もあります。そのため、災害時以外の通常業務でも利用できる機能があるかどうかは、システムを「活きたツール」にするカギとなります。
例えば、
- 業務連絡や緊急通達への応用
- 出勤・在宅勤務の報告機能
- 社内アンケートや情報収集
などに使えると、従業員がシステムに慣れ、災害時にもスムーズに動けるようになります。
6.コストと導入のしやすさ
もちろん、費用対効果も見逃せません。導入初期費用、月額料金、ユーザ数に応じた課金体系などを把握し、自社の規模や予算に合うかを検討しましょう。
一部のサービスでは、トライアル利用やデモが可能な場合もあります。実際に触れてみてから判断するのも賢いやり方です。
まとめ:最適なシステム選定が、安心と行動を支える
「安否確認」はBCPにおける「最初の行動」です。だからこそ、選んだシステムが「確実に動く」ものであることが、従業員の命、そして事業の継続を左右するといっても過言ではありません。
「安否確認」という視点で見れば、選定の際には「使えるかどうか」に加えて、「信頼できるかどうか」が問われるのです。
次章では、こうしたチェックポイントを踏まえたうえで、企業がすぐに始められるBCP対策についてご紹介します。小さな備えが、大きな安心につながる第一歩となります。
企業が今すぐ取り組むべきBCP対策

ここまで、「安否確認」や「安否確認システム」の重要性、導入事例、システム選定のポイントについて見てきました。最終章となる本章では、企業が今日から実践できる「第一歩」としてのBCP対策を、できるだけ具体的にお伝えします。
「BCPは大企業だけのもの」と思われがちですが、実際には規模に関係なく、すべての組織が取り組むべき課題です。なぜなら、災害や突発的な危機は、会社の大小を問わず平等に訪れるからです。では、どこから始めれば良いのでしょうか?
1.まずは「安否確認体制の棚卸し」から始めよう
現在、自社では災害発生時に従業員の安否をどのように確認しているのか、確認してみましょう。
- 連絡網(電話・メール)で個別に確認している
- チャットアプリを使って確認している
- そもそも明確なルールがない
こういった状況のままでは、実際の災害時に情報が混乱し、対応が後手に回ってしまいます。まずは「今の安否確認のやり方で、本当に大丈夫なのか?」を確認し、課題点を洗い出すことがスタート地点です。
2.「安否確認システム」の導入・比較検討を進める
「安否確認システム」の導入は、人的資源を守るうえで非常に効果的な対策です。すでに多くの企業がその効果を実感しており、導入のメリットは前章でも触れました。
比較検討の際は、以下の点を重視してみましょう。
- 直感的な操作性(誰でも使いやすいか)
- 複数の連絡手段(メール、SMS、アプリなど)
- 回答状況の可視化と管理のしやすさ
- 日常利用への拡張性(業務連絡などに活用できるか)
- コストと導入の手軽さ
いきなり本格導入が難しい場合でも、無料トライアルを活用して現場に試してもらうだけでも、社内に「BCPってこういうものなんだ」という実感が生まれます。
3.定期的な訓練とルールの明文化を行う
システムを導入するだけで終わらせず、「使い方を定着させる仕組み」も必要です。特に重要なのが、定期的な安否確認訓練です。
例えば、
- 年2回、全社員を対象とした安否確認訓練を実施
- 非常時のマニュアルを整備し、社員に共有
- 実施結果をふりかえり、課題を改善
これにより、「本当に災害が起きたとき、社員が迷わず動けるか」を確認し、制度として根づかせることができます。
また、災害対応のルールやフローを社内規定やBCP文書として明文化しておくことも非常に大切です。口頭ベースで運用している企業も多いですが、いざというとき「誰が・何を・どう動くか」を明示しておくことで、初動対応の速さが大きく変わります。
4.社内全体で「BCPの意識」を育てよう
BCP対策は、経営者や総務部門だけが取り組むものではありません。実際に動くのは、現場の従業員一人ひとりです。だからこそ、BCPの必要性や安否確認の重要性を、全社員に浸透させる工夫が求められます。
例えば、
- 朝礼や社内報でのBCP情報の共有
- BCP研修や防災セミナーの実施
- 実際の災害事例を用いたケーススタディ
といった形で、日頃から「災害は誰にでも起こる」という意識づけを図ることが、いざというときの連携力につながります。
5.外部パートナーとの連携も忘れずに
BCPを考えるうえで、従業員の安全だけでなく、取引先や協力会社との関係も重要です。大規模災害が起きたとき、連携先の状況が不明確だと業務の継続に支障をきたす可能性があります。
そのため、安否確認の範囲を協力会社・委託先にも広げることを検討してみましょう。共有システムを使えば、取引先の担当者の無事も把握でき、業務調整のスピードがぐっと上がります。
最後に:小さな一歩が、大きな安心につながる
BCP対策は決して大げさなものではなく、「社員を守るために何ができるか?」というシンプルな問いから始まります。そして、その答えの一つが安否確認の仕組みを整えることなのです。
今回ご紹介したような取り組みは、どれも明日からでも始められることばかりです。「備えあれば憂いなし」ではなく、「備えがなければ動けない」時代に、今こそ一歩を踏み出すべき時なのかもしれません。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。
- 事業内容
- デジタルマーケティング支援
デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格
- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)
プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))
ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)