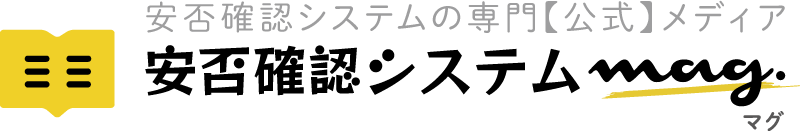大事な従業員を守るために・・・過去の地震から学ぶ安否確認の備え方
2025/05/08(2025/11/28).

突然の地震が発生したとき、大切な家族や同僚の安否確認はどうしますか?
地震発生の混乱で、スマートフォンの通信が混雑してつながりにくくなったり、すぐの連絡が取れなくなったりすることは珍しくありません。そんなとき、事前に適切な安否確認の仕組みを導入しておけば、スムーズに安否情報を確認し、迅速な対応が可能になります。
本コラムでは、過去の大型地震の事例をもとに、地震時の安否確認の重要性や課題を解説し、最適な安否確認の方法について考えます。さらに、安否確認システムの種類や特徴を比較し、企業や家庭で活用する際の選び方や準備のポイントを紹介します。
「万が一のとき、大切な人とすぐに連絡が取れるだろうか?」そんな不安を少しでも解消するために、今こそ準備を始めてみませんか?本コラムを通じて、地震への備えを見直し、安心できる安否確認の方法を一緒に考えていきましょう。
index
地震発生時に企業が直面する安否確認の課題

地震はいつ起きるかわからない自然災害であり、企業にとっても大きなリスクです。中でも従業員の安否を確認することは、企業活動の再開やBCP(事業継続計画)を進めるうえで最初に取り組むべき重要なステップです。しかし、実際には地震発生時の安否確認には多くの課題が存在します。
連絡手段の混乱と情報収集の遅れ
地震が起こると、多くの人が一斉に連絡を取り合おうとするため、電話回線や通信インフラが一時的に混雑します。この状態を「輻輳」(ふくそう)と言います。輻輳が発生すると携帯電話がつながらなかったり、メールやメッセージの送受信に遅れが生じたりといった現象が発生します。こうした状況では、企業が従業員と連絡を取り合い、正確な安否情報を集めることが難しくなります。
さらに、在宅勤務や外回りなど、従業員の働き方が多様化している現代では、オフィス外にいる人の状況を把握するのが一層困難になります。
手作業による確認の限界
いまだに電話やメール、紙のリストを使って安否確認を行っている企業もありますが、これでは対応に時間がかかり、情報の漏れや重複が発生しやすくなります。特に従業員数が多い企業ほど、こうした手作業では対応しきれません。加えて輻輳が発生すると更に時間がかかり、全ての情報が揃うのに数日かかることもあります。
このため、情報の集約や管理が煩雑になり、迅速な対応が求められる災害時には非効率的な方法と言えます。
安否確認システムの導入率と運用のギャップ
安否確認システムを導入している企業も増えていますが、「導入しているだけ」で満足してしまい、運用が形骸化しているケースも少なくありません。
例えば、定期的な訓練をしておらず、従業員が使い方を覚えていなかったり、通知が来ても反応しなかったりといったケースがあります。これでは、せっかくのシステムも意味をなしません。
導入したシステムを有効に活用するには、事前のルール作りや継続的なトレーニングが欠かせません。
BCPとの連携が弱いことによる対応の遅れ
安否確認は従業員の安全を守るだけでなく、BCPを迅速に動かすためのカギでもあります。誰が出社できるのか、どの部署が稼働できるのかを早期に把握することで、業務再開の判断がしやすくなります。
しかし、安否確認の結果をBCPの各フェーズにどうつなげていくかが明確でない企業も多く、情報を収集しても活用されないまま時間が過ぎてしまうという課題もあります。
いま、見直すべき安否確認のあり方
地震が起きたとき、企業にとって従業員の安否確認は最優先事項です。しかし、通信の混乱や手作業の限界、運用不足など、さまざまな課題が立ちはだかります。
これらを解決するためには、安否確認システムの導入と運用体制の整備が不可欠です。単にシステムを入れるだけでなく、「いざという時に本当に使えるかどうか」を見直すことが、企業にとっての大きな備えになるでしょう。
過去の震災に学ぶ企業の安否確認対応の教訓

地震が発生したとき、企業は何よりもまず従業員の安否を把握し、安全を確保することが求められます。では、実際に大規模地震が起きたとき、企業はどのように安否確認を行っていたのでしょうか?過去の震災事例を振り返ることで、今後に活かせる重要な教訓が見えてきます。
東日本大震災:想定を超えた混乱と、情報伝達の限界
2011年の東日本大震災では、多くの企業が地震による被害だけでなく、従業員との連絡が取れないという大きな課題に直面しました。
当時、まだ安否確認システムを導入している企業は少なく、多くが電話やメール、社内連絡網に頼っていました。しかし、通信回線の混雑や停電の影響で、連絡がまったく取れず、安否確認に数時間から数日かかった企業もありました。
【教訓】
想定外の事態でも情報を確実に集められる仕組みが必要だということ。電話やメールだけに頼らず、複数の手段を備えた安否確認システムの重要性が広く認識されるようになりました。
熊本地震:システム導入が奏功した例も、課題も明らかに
2016年の熊本地震では、安否確認システムを導入していた企業も多く、比較的スムーズに対応できた事例が報告されています。
例えば、ある企業では地震発生後すぐに安否確認システムを通じて一斉通知を配信。多くの従業員がスマートフォンから数分以内に回答し、社内の安全確認とBCPの立ち上げが迅速に行われました。
しかし一方で、「訓練していなかったため、操作方法がわからなかった」、「通知が来ていることに気づかなかった」など、運用面での課題も浮き彫りになりました。
【教訓】
システムは導入して終わりではなく、従業員への周知と定期的な訓練が不可欠であることが明確になりました。
能登半島地震(2024年):連絡手段の「ギャップ」が浮き彫りに
2024年に発生した能登半島地震では、特にノンデスクワークの業種を中心に、安否確認の仕組みが不十分な企業が多く見られました。
ある調査(※)では、対象者の約半数が「災害時の安否確認手段が定まっていない」「よく分からない」と回答しています。また、多くの従業員は「安否確認専用システムを使いたい」と希望している一方で、企業側は未だに「電話」や「メール」に依存しているケースが目立ちました。
※株式会社アルダグラム「ノンデスクワーク業界の災害時安否確認に関する実態調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000058603.html?utm_source=chatgpt.com)
【教訓】
デスクワーク中心の企業と現場作業が多い業種では、使いやすさや導入のしやすさも異なるため、一律の仕組みでは対応しきれないという現実が明らかになりました。現場の実態に即した方法を選ぶことが大切です。
過去の震災から学べる共通のポイント
これらの震災を通じて、企業が学ぶべき共通点は次の3つに集約されます。
- 通信障害を前提にした多様な手段の確保
メール、SMS、アプリ、SNSなど複数のルートで安否確認を行う体制が重要。 - 安否確認システムの導入と訓練の両立
システムを導入しても、使えなければ意味がない。操作方法の共有と定期的な訓練が必要。 - BCPとの連携
安否確認の結果は、業務再開判断や社員の支援体制の構築に直結する。BCP全体の中で安否確認を位置付けることが大切。
過去の地震は、未来の備えに変えられる
過去の地震で見えてきたのは、「準備の有無が結果を大きく左右する」という現実です。安否確認が遅れることで、安全確認が遅れ、BCPの発動も遅れてしまいます。
企業として、システムの導入はもちろん、運用体制や現場に合った方法の検討、訓練の積み重ねが必要不可欠です。過去の震災から得た教訓を、自社の仕組みにどう活かすか――その視点が、これからの企業防災に求められています。
次章では、安否確認システムの種類と選定基準について、具体的に見ていきましょう。
安否確認システムの種類と選定基準

地震のような自然災害が発生したとき、企業がまず最優先で取り組むのが従業員の安否確認です。そのために欠かせないのが「安否確認システム」。しかし、世の中にはさまざまなシステムが存在しており、どれを選ぶべきか悩まれる企業も少なくありません。
本章では、安否確認システムの主な種類と、それぞれの特徴、そして企業が選ぶ際のポイントについてわかりやすくご紹介します。
安否確認システムの主な種類
現在、企業向けに提供されている安否確認システムは、大きく分けて以下の4つのタイプに分類できます。
■クラウド型システム
最も多くの企業が導入しているのがこのタイプです。インターネットを通じて、自動、もしくは管理者による手動での一斉通知を行い、従業員がスマートフォンやPCなどから安否を報告します。
- 特長
- 一括管理ができ、集計がしやすい
- 通信手段が複数ある(アプリ・メール・SMSなど)
- BCPとも連動しやすい
- 注意点
- 導入・運用コストがかかる
- 操作に慣れていないと、いざというときに使えない可能性も
■メール・電話連絡網型
昔ながらの連絡網をベースにしたシンプルな方法です。従業員同士で安否を確認し合い、情報を上へ集約していきます。
- 特長
- 導入コストがほとんどかからない
- 小規模事業所などで手軽に使える
- 注意点
- 人手と、安否の確認が揃うまでの時間がかかる
- 地震時の通信障害に弱く、連絡が取れないことも
■チャット・SNS連携型
LINEやSlack、Microsoft Teamsなどのツールを利用した方法です。普段から使用しているツールを活用するため、抵抗感が少ないのが魅力です。
- 特長
- 操作が簡単で即応性がある
- 既存ツールの延長線上で利用できる
- 注意点
- 専用の安否確認システムに比べると集計機能が弱い
- セキュリティや管理責任が曖昧になりやすく個人情報の流出などのリスクが高い
■GPS連動型
スマートフォンの位置情報を使って従業員の現在地を把握する仕組みです。災害時に自分で報告ができない状況でも、ある程度の所在確認が可能になります。
- 特長
- 回答がなくても、ある程度の状況が把握できる
- 外回りや現場作業の多い職種に向いている
- 注意点
- プライバシーの問題から従業員の理解が必要
- GPSが正確でない場所では機能しにくい
システム選定のポイント
企業が自社に最適な安否確認システムを選ぶ際は、ただ機能が多いものを選ぶのではなく、自社の「規模」「業種」「働き方」に合ったシステムかどうかを見極めることが大切です。
- 企業規模と従業員数に合っているか
- 小規模企業なら、メールやチャットを活用した低コスト型でも対応可能
- 中~大規模企業には、一斉通知・自動集計が可能なクラウド型が最適
- 通信障害時の対応ができるか
- 地震時は電話がつながりにくくなるため、メール・アプリ・SMSなど複数の通信手段に対応しているかがカギになります
- 管理者の負担が少ないか
- 操作が分かりやすく、誰でも使いやすいUIになっているか
- 回答状況をリアルタイムで一覧管理できるかどうかも要チェックです
- 従業員にとって使いやすいか
- 日頃から利用しているツールと連携していると、緊急時のハードルが下がります
- アプリのダウンロードや初期設定が簡単かどうかもポイント
- BCPと連動できるか
- 安否確認結果をもとに、避難や業務再開の判断がスムーズに行える仕組みになっていると理想的です
- 安否確認結果をもとに、避難や業務再開の判断がスムーズに行える仕組みになっていると理想的です
企業向けに最も適した安否確認システムとは?
さまざまなシステムがありますが、企業向けに最もバランスが取れており、幅広い業種・規模に対応できるのがクラウド型の安否確認システムです。
- 複数の連絡手段に対応し、通信トラブルにも強い
- 従業員の安否状況を一元管理でき、BCPの判断材料にも直結する
- 拠点が複数ある企業やテレワークが多い職場でもスムーズに運用できる
もちろん、すべての企業にとって万能というわけではありませんが、現代の働き方やBCPの観点から見ても、最も汎用性が高いのがこのタイプです。
自社に合ったシステム選びがカギ
安否確認システムは「備え」ではありますが、実際に地震が起きたとき、その価値が本当に試されます。大切なのは、「導入すること」ではなく、「使いこなせること」。そして、自社の環境や従業員の働き方にフィットしたシステムを選ぶことが、迅速かつ正確な安否確認の第一歩です。
次章では、導入後の運用を成功させるために、企業が押さえておきたいポイントについて解説していきます。
企業が安否確認システムを導入する際のポイント

安否確認システムは、地震などの災害時に従業員の安全を素早く把握するために欠かせないツールです。とはいえ、「とりあえず導入した」というだけでは、本当に有効な運用とは言えません。
この章では、企業が安否確認システムを導入する際に、効果的に活用するために押さえておくべきポイントを整理してご紹介します。
目的を明確にすることから始めよう
まず大切なのは、「なぜ安否確認システムを導入するのか」という目的を明確にすることです。
たとえば、「従業員の安全を確保したい」「災害時の混乱を最小限にしたい」「BCPの初動をスムーズにしたい」など、目的が明確になっていれば、必要な機能や運用の方向性も見えてきます。
導入ありきではなく、「何を達成したいか」から逆算する姿勢が成功のカギになります。
自社の状況に合ったシステム選びを
世の中には多くの安否確認システムがありますが、企業の業種や規模、働き方によって適したシステムは異なります。
たとえば、テレワークや外勤の多い企業なら、スマートフォンやアプリで手軽に回答できるクラウド型のシステムが向いています。一方、小規模なオフィスや店舗なら、メールやLINEなど身近なツールのほうがスムーズな場合もあります。
重要なのは、自社に合った運用ができるかどうか。機能が多すぎて使いこなせないシステムでは、本番で混乱を招くことも。
必要十分な機能を備えたシンプルなツールを選ぶのも、立派な選択肢です。
運用フローとルールをしっかり整備する
システムを導入しただけでは、いざというときに動きません。明確な運用フローとルールの整備が必要です。
たとえば、
- 地震が起きたら誰がシステムを起動するのか
- 通知は何分以内に送るのか
- 回答は何時間以内に完了することを想定するのか
こうした「行動の基準」を具体的に定めておくことで、災害時の迷いを減らし、全体の動きを早くすることができます。
また、未回答者へのフォロー体制も重要です。再通知のタイミングや、個別連絡の担当者をあらかじめ決めておくことで、対応漏れを防げます。
従業員への周知と教育が成功のカギ
どんなに優れた安否確認システムでも、従業員が使えなければ意味がありません。導入時には操作方法をしっかり説明し、実際に使ってみる機会を設けることが大切です。
操作ガイドを配布するだけでなく、短時間でも「実際に通知を受け取って、安否を報告してみる」といった簡単な訓練を行うと、理解が格段に深まります。
また、定期的な訓練によって「安否確認は自分の役割なんだ」という意識を従業員に持ってもらうこともポイントです。日頃から備えておくことが、地震などの非常時での混乱を抑えることにつながります。
BCPと連携した運用設計を意識する
安否確認システムは、単体で完結するものではありません。BCPとの連携を前提にした運用設計が重要です。
例えば、安否確認の結果をもとに、
- 出社できる人員でどの業務を優先的に再開するか
- 避難が必要な拠点の判断
- サポートが必要な従業員への対応
といったアクションにつなげていくことが、システムの真価を発揮するポイントです。BCPの発動手順の中に、安否確認をどう位置づけるかも検討しておきましょう。
費用対効果と継続運用の視点も忘れずに
最後に見落としがちなのが、導入後のランニングコストや継続運用の視点です。
初期導入費用が安くても、運用に手間がかかりすぎては長続きしません。反対に、多少コストがかかっても、管理がラクで従業員にも定着しやすいシステムであれば、結果的に「安くつく」こともあります。
また、システムは時間とともに更新が必要になることもあるため、ベンダーのサポート体制や将来的な拡張性などもチェックしておきましょう。
導入はスタートライン。活かすための準備をしよう
安否確認システムは、災害時の命綱のような存在です。ですが、入れるだけで安心するのではなく、「どう運用するか」「どう従業員に定着させるか」が、システムの価値を左右します。
目的を明確にし、自社に合ったシステムを選び、ルールと訓練を整えてこそ、地震などの緊急事態に真の力を発揮してくれるのです。
次章では、導入した安否確認システムを活かすための「事前準備と訓練」の大切さについて、さらに深掘りしていきます。
迅速な安否確認を実現するための事前準備と訓練

どれだけ優れた安否確認システムを導入しても、いざ地震などの災害が起きたときにきちんと機能しなければ意味がありません。スムーズな安否確認を実現するには、「事前準備」と「定期的な訓練」が欠かせません。
この章では、安否確認システムを災害時にしっかり機能させるために、企業が平常時から取り組むべき準備と、効果的な訓練のあり方について紹介します。
安否確認のフローを明確にする
最初に行うべきは、地震発生時にどのような流れで安否確認を行うかという「基本フロー」の整備です。
例えば以下のような流れを、あらかじめ定めておくことが重要です。
- 地震発生の情報をキャッチした時点で安否確認システムを起動
- 全従業員に一斉通知を配信
- 従業員が各自の状況を報告(無事・負傷・避難中など)
- 回答がない従業員への再通知・フォロー連絡
- 安否情報の集約とBCPチームへの報告
この一連の動きを「誰が、いつ、どのように」担うのかまで落とし込んでおくことで、災害時の対応に迷いがなくなります。
管理者と担当者の役割分担を決めておく
安否確認の対応は1人で完結できるものではありません。複数名で支え合い、素早く対応できる体制を整えておくことが大切です。
たとえば以下のような役割分担があるとスムーズです。
- システム管理者:設定・配信・トラブル時の初期対応
- 部門責任者:自部門の従業員の安否確認状況の把握
- BCP担当者:集まった情報を基に事業継続の判断を行う
また、1人に負担が偏らないよう、「代行者」もあらかじめ決めておくと、災害時の不在にも対応できます。
未回答者への対応ルールを決める
安否確認でよくあるのが、「通知はしたけど、全員からの回答がそろわない」という状況です。こうした事態に備えて、未回答者にどうアプローチするかを決めておきましょう。
たとえば、
- 一定時間後に再通知(自動または手動)を送る
- 担当者が電話やSMSで個別に連絡する
- 最終的に家族や緊急連絡先へ連絡するルールを設ける
地震直後はパニックや通信不良も起きやすいため、「絶対にすぐ返答がある」と期待せず、柔軟に確認を重ねる体制が重要です。
また、未回答者が何らかの理由で回答を送信できない状況だった場合は、直接聞き取った安否回答を管理者が代理で入力できるシステムを導入すると、後の集計時に便利です。
定期的な訓練で「慣れておく」ことが重要
訓練は、災害対応の精度を高める上で欠かせません。特に安否確認は、普段あまり使う機会がないため、定期的に操作を体験する機会を設けることが大切です。
年1回でも構いません。「地震が起きた」という想定で実際に通知を送り、従業員に安否を報告してもらいましょう。管理側も同時に、情報集約・未回答者の確認・BCPとの連携までを一通り流してみるのがおすすめです。
訓練を重ねることで、「自分の役割」が自然と身につくようになり、災害時の混乱もぐっと減らせます。
訓練後の振り返りと改善もセットで
訓練をしたあとは、その結果を必ず振り返りましょう。「どれだけの人が何分以内に回答したか」「操作に戸惑った人はいたか」「管理側の対応に漏れはなかったか」などを記録しておくと、次回への改善点が見えてきます。
改善点が見つかれば、それを次の訓練に反映。こうして少しずつ精度を高めていくことで、企業全体としての「災害対応力」が確実に強くなっていきます。
従業員の意識を高めるコミュニケーションも大切に
どれだけ体制が整っていても、最終的に安否確認を実行するのは「人」です。だからこそ、従業員一人ひとりが「安否確認の意味」や「自分の役割」を理解していることが何より重要です。導入時や訓練時には、安否確認の背景や目的についても丁寧に説明しましょう。
たとえば、
- どんなときに通知が来るのか
- 自分が報告しないと何が起こるか
- 企業としてどんな対応をしていくのか
といった点を共有することで、ただの「システム操作」ではなく、「自分と周囲を守る行動」であることが伝わります。
使える仕組みに育てるのは「日頃の準備」
地震のような突然の災害が起きたとき、安否確認がスムーズにできるかどうかは、日頃の準備と訓練にかかっています。
システムの導入はあくまでスタート地点。フローや体制を整え、従業員と一緒に訓練を重ねることで、はじめて「使える仕組み」へと育っていきます。
万一のときに慌てず動けるように、今こそ一度、自社の準備状況を見直してみませんか?

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。
- 事業内容
- デジタルマーケティング支援
デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格
- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)
プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))
ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)
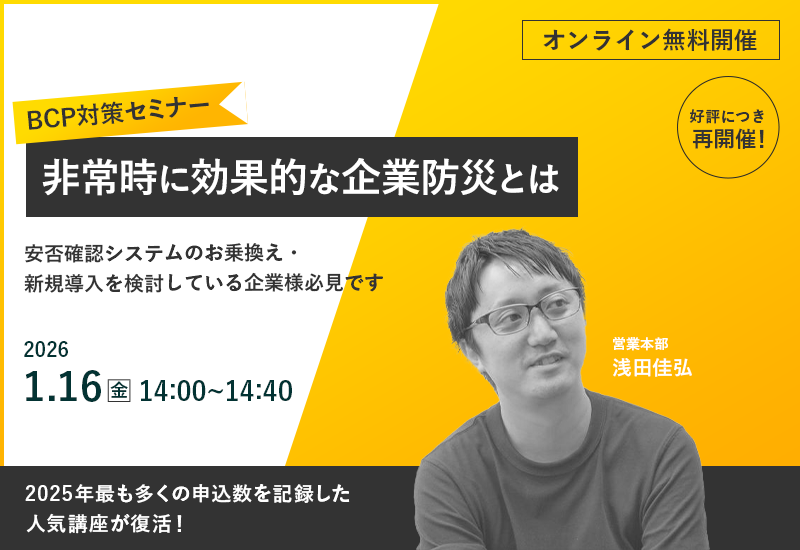
- 2025.12.25
1/16(金)【再演決定!】2025年最も多くの申込数を記録した人気講座が復活!『BCP対策セミナー 非常時に効果的な企業防災とは』 
- 2025.12.17
安否コール、~誰にでもすぐ届く~新機能「SMS Alert」誕生 「6割以上が体験したい!」、選ばれる新時代の安否確認システム 
- 2025.12.10
【国内最大級の竜巻災害と支援制度】BCP NEWS Letter 
- 2025.12.09
安否確認システム「安否コール」、コミュニケーションツールに関する意識調査を実施 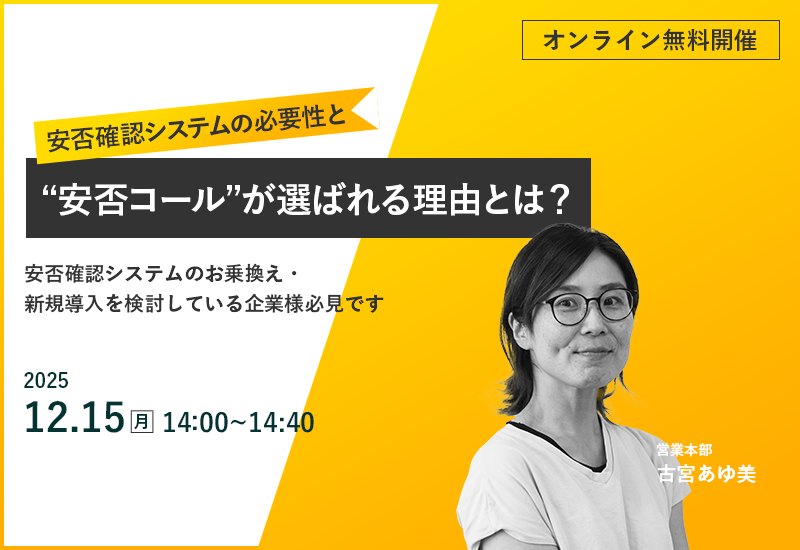
- 2025.12.03
12/15(月)【オンラインセミナー】安否確認システムの必要性と“安否コール”が選ばれる理由とは?